|
|
 |
| 1.「つみき教材」とは・・・ 幼児期に大切なことは知能のはたらきを高めることです。あそびを通じて適切な刺激を与え、知能の働きを充分に伸ばすことによって、知能を備え、活発で、創造力のある子どもに育っていくと言われています。 「つみき教材」は全日本知能開発研究会会長の川野康行氏が、アメリカの心理学者ギルフォード博士の知能構造論を基に開発したものです。約10種類の「つみき」という具体物を使いながら、脳の前頭葉をはじめ右脳と左脳をバランスよく刺激し、子どもたちの様々な可能性を拡げて行く知育教材となっています。①イメージ力(頭の中で思い描く力) ②転換力(色々な角度からものを捉える力) ③論理力(順序よく考えたことを整理する力) ④記憶力(覚えたものを引き出す力) ⑤評価力(正しいことを判断する力) ⑥見通す力(行動の予測をたてられる力) 以上のようなことを「つみき教材」を通して学ことができます。 2.ギルフォード博士の知能構造論 大脳の成長が顕著な幼児期に脳の機能を繰り返し訓練する ギルフォード博士は知能には3つの側面があるという「知能構造論」を1950年に発表しました。 これは知能の複雑で精妙なしくみを分析的かつ統合的に捉えた非常に優れた理論です。 知能の3つの側面とは、「考える領域」「考える働き」「考える所産」を言います。そして、この3つの側面に含まれる具体的な要素の組み合わせを知能因子と呼びます。 右上図の知能因子の具体的な読み方は「領域」で「所産」を「働き」するとなります。例えば、(図形)で(単位)を(認知)すると読みます。 |
|
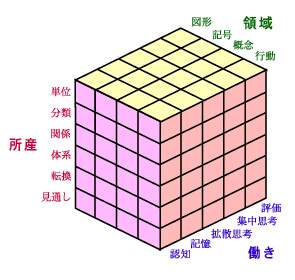 ことによって、知能がどんどん伸びることは科学的に実証されています。
ことによって、知能がどんどん伸びることは科学的に実証されています。